2024年2月27日、LenovoはCore Ultra Series 1を搭載した14インチノート「ThinkBook 14 Gen 7」を発売しました。
スペック

| ■ ThinkBook 14 Gen 7 | |
| CPU | Core Ultra 7 155H Core Ultra 7 155U Core Ultra 5 125H Core Ultra 5 125U |
|---|---|
| メモリ | 8~16GB DDR5-5600 |
| ストレージ | 256GB~1TB Gen4 SSD |
| 画面 | 14.0インチ IPS WUXGA(60Hz) |
| インターフェース | USB Type-C(TB4)×1 USB Type-C(Gen2)×1 USB 3.2 Gen1×2 HDMI 1GbE 有線LAN SDXC オーディオジャック |
| wi-fi | Wi-fi 6E+BT5.3 |
| バッテリー | 45/60WHr |
| サイズ | 313.5×224×16.9mm |
| 重さ | 1.38kg |

自由テキスト
特徴
「ThinkBook 14 Gen 7」はThinkbookとしては2機種目の、Core Ultra Series 1搭載ノートです。
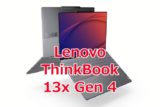
Lenovo全体だと「IdeaPad Pro 5i Gen 9」など、他にも採用機種はいくつかあります。

CPU
「ThinkBook 14 Gen 7」の搭載CPUはCore Ultra Series 1からCore Ultra 7 155H/155UまたはCore Ultra 5 125H/125Uを搭載します。

Core UltraはCPUコアを4nm相当のIntel 4、それ以外を5nm/6nmのTSMC N5/N6で製造する、タイル(チップレット)構造となっています。
ハイブリッドアーキテクチャはP+E+LP Eの3層になり、グラフィックアーキテクチャがIntel ArcベースのXe-LPGに、さらにNPUも内蔵しました。
UシリーズとHシリーズはベースTDP(Uシリーズ:15W,Hシリーズ:28W)だけでなく、Uシリーズは12コア14スレッド(2P8E2LPE)で、Hシリーズは125Hが14コア18スレッド(4P8E2LPE)、155Hが16コア22スレッド(6P8E2LPE)と、CPUのコア構成自体が違います。
ついでに言うとUシリーズはグラフィックが4Xeコアで、Hシリーズは8Xeコアまたは7Xeコアなので、グラフィック性能も大きく違います。
Core Ultra 7 155UおよびCore Ultra 5 125Uはデータが少なく、特にグラフィックベンチマークは見当たりませんでした。
Core Ultra 7 155UとCore Ultra 5 125Uは構成が同じで動作周波数が違うだけなので、PassMarkスコアは12~15%くらいの差になると思われます。Core Ultra 7 155Uは推定21000~22000程度ってことですね。
グラフィックは、Core Ultra 7 155HがRyzenを追い抜いて、内臓グラフィックのトップに。Core Ultra 5 125HでもRyzen 7 7840Uと同等です。
UシリーズだとCore Ultra 7 155H(8Xe)の半分のXeコアしかないので、推定で6割程度。5300~5400くらいのスコアでしょうか。
メモリとストレージ
メモリは8GBまたは16GBのDDR5-5600。
内部は2スロットで、16GBの場合は8GB×2と16GB×1の場合があります(モデルごとに記載されています)。
実はここ結構重要で、Core Ultraでは内臓グラフィックがIntel Arcを名乗れるのはメモリが16GB以上かつデュアルチャンネル以上の時と決められています。
そして割と仕様表の表記が適当なLenovoにしては珍しく、きっちり書き分けられていて変に感動したり。
ストレージは256GBから1TBのGen4 SSD。2242サイズで、TLC NANDであることが明記されています。
その他
無線LANはWi-fi 6E(802.11ax)に対応。Bluetoothはv5.3。
有線LANは1GbEを内蔵しています。
Thinkbookの位置づけはIdeaPadとThinkPadの中間なので、こうして有線LANが残っているあたりにThinkPadみが感じられます。
バッテリーは3セルの45WHrまたは4セルの60WHr。CPUにHシリーズを選ぶと強制的に60WHrとなります。
駆動時間は4K動画の連続再生で9.5時間、アイドル時は17.3時間(JEITA 3.0)。
アイドル時はLP Eコアでの動作となるので、Core Ultra搭載機はアイドル時の駆動時間がやたらと長くなります。
電源アダプタは65Wまたは100W。充電時間は約2時間です。
45WHrは30分で50%、60WHrは1時間で80%の急速充電に対応しているとのこと。
外観

外観は標準的なThinkbook筐体というか、「ThinkBook 14 Gen6」と同じものと思われます。
サイズも同じですし。
ディスプレイは14インチWUXGA(1920×1200)。
面白いのが、Core Ultra 5モデルでは45%NTSCなのに対し、Core Ultra 7では100% sRGBと差が付けられています。
Webカメラは1080pでIRカメラはなし。生態認証は指紋リーダーでの対応となります。

2.Powered USB 3.2 Gen 1
3.HDMI
4.Thunderbolt4
5.コンボジャック
7.USB 3.2 Gen 1
8.RJ-45
9.ケーブルロックスロット(2.5x6mm)
インターフェース構成も「ThinkBook 14 Gen6」そのまま。Thunderbolt4を含むType-Cが2ポート、Type-Aが2ポート。カードリーダーはフルサイズのSDXCリーダーとなっています。
超薄型でThunderbolt4×3だけだった「ThinkBook 13x Gen 4」と違い、ビジネス寄りの端子構成ですね。

「ThinkBook 14 Gen6」から引き続き、ThinkPadとIdeaPadの相の子みたいなキーボード。PgUP(PageUp)/PgDN(PageDown)キーがあるのとないのでは大違いです。
1点だけ変更があって、右CtrlがCoPilotボタンに変更されています。

Thinkbookの特徴であるツートンカラー天板。

サービスマニュアルより、内部図。
何気にSSDが2スロットありますね。PSREFで確認したところ、デュアルGen4 SSDとなっていました。
参考 ThinkBook 14 G7 IML:Lenono PSREF
まとめ
「ThinkBook 14 Gen 7」の価格はCore Ultra 5 125Uモデルが110,704円から、125Hモデルが113,652円から。
125HモデルはカスタマイズでOSをWIndows 11 Homeにすることで108,108円まで下げられます。Core Ultra 7 155Hだと124,740円から(メモリは8GBなので、十全に使うなら増設必須です)。
他の機種だとCore Ultra 7 155Hモデルは15万円くらいからなので、とんでもない破格値という。
価格差が思ったほどではないのでCore Ultra 7 155Hもアリですが、性能表を見て分かるように、Core Ultra 5でもHシリーズならCPU・グラフィックともに十分な性能を持っています。なんなら中量級のゲームくらいならプレイできます(ディスプレイは60Hzですが)。
薄型とか2.2K液晶とか、そういったハイエンド要素は持っていないものの、後からメモリを増設できますし、価格バランスは非常にいいというか、かなり安価な機種と言えます。
ThinkBookだけどこれは人気が出るんじゃないかな。
関連リンク


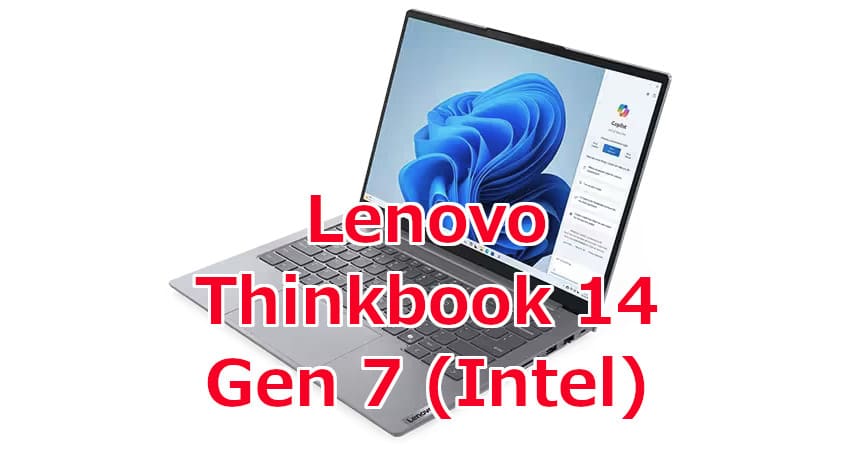


コメント